プロジェクト紹介01【NEON JAPAN】 PROJECT 01
チームで創り上げた挑戦の記録。
2025年3月。かつて回転式の客席を備えた円形の劇場として使われていた建物に新たな命が吹き込まれた。舞台は東京・豊洲。
劇場から体験型エンターテイメントの新たな拠点へと再生させる大規模改修プロジェクトを、サンケイビルテクノが設計・施工の両面から手がけた。
この施設は、体験型エンターテインメント事業を世界的に牽引するシンガポール企業・NEON、伊藤忠都市開発、サンケイビルによるジョイントベンチャー「NEON JAPAN」が手がける、日本第一弾の体験型エンターテイメント施設である。世界的な展示企画『ラムセス大王展』の日本初開催に向けて、劇場から展示空間への大胆な用途の転換、既存建物の特性を活かした設計、防火や法規制との折り合い──。様々な課題が立ちはだかる中、営業・設計・施工が部署の垣根を超えて手を取り合い、“最適解”を模索していった。
それぞれの専門性が交差する中で、チームの中心にいたのは営業のK.K、設計のT.W、施工のK.S。これは、一つの建物と一つのチームが、“変化”を恐れず前に進んだ一年間の軌跡だ。
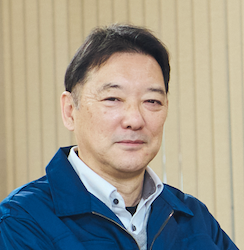
- K.S(2023年中途入社)
建築部 担当部長【担当|所長・施工管理】

- K.K(2021年中途入社)
建築部 担当課長【担当|営業】

- T.W(2022年中途入社)
設計部【担当|設計・監理】
“やったことがない”を“できるように導く”。
それが、営業としてのミッションだった。
プロジェクトを牽引したのは、営業担当のK.Kだった。彼女の役割は、施主の要望を的確に読み取り、サンケイビルテクノがその期待に応えられるかどうかを社内で詰めていくこと。金額面、スケジュール、法的制限──すべての調整が必要だった。
「設計と施工の両方を担う“設計施工一括受注”は、実はサンケイビルテクノでは初めてのケースでした。社内での調整や関係各所とのやりとりが非常に多く、提案段階から細かく金額やスケジュールをすり合わせる必要があり、正直、とても大変でしたね…。とにかく“できること”“できないこと”を明確にして、社内外の調整に奔走しました」
実施設計で求められたのは、
創意工夫力と読み解く力。
設計を担当したのは、2022年にサンケイビルテクノに中途入社したT.W。前職では主に新築マンションの設計を手掛けてきた。この改修工事を通じて「既存建物をどう活かすか」という設計の本質に触れ、大きな学びを得たという。
「劇場という特殊用途で、かつ不特定多数の来場者が利用する場所ですから、段差やスロープの設計、安全基準など、細かいところまで神経を使いました」
また、設計段階での法的な読み解きも課題となった。建築基準法や消防法の要件を満たすために、管轄の消防署に何度も足を運び、設計部内でも法解釈についての議論が重ねられた。
「劇場は一般のビルとは全然違うんです。各工程で細部にわたる確認を行い、慎重に進めました」
止まってはいけない現場でどう動くか。
施工管理を担ったのは、現場所長としてプロジェクトを統括したK.S。前職ではゼネコンで所長として複数現場を統括し、数多くの大規模工事を手がけてきたベテランである。今回のプロジェクトでは3名のチームを率いて、現場の安全・品質・工程管理に奔走した。
「私自身のこれまでの経験からすれば、施工内容そのものは複雑な部類ではありませんでしたが、“生きている建物”の中で、電気やセキュリティが稼働している中、工事を進めるというのは、常に気を配り続けなければならない繊細な作業だったと思います」
実際の施工においては、空調設備のルート変更や展示主導のレイアウト変更など、進行中に発生した調整も多かった。
「前職のゼネコンでは、営業担当は契約後ほとんど現場に関わらず、施工管理側が一手に折衝を担うのが当たり前でした。でも、このプロジェクトで営業を担当したK.Kさんは違いました。契約後も一貫して関わり、現場で起きる細かな調整やクライアントとのコミュニケーションも担ってくれたのです。営業としてプロジェクトが円滑に進むよう、自ら手を動かして支えてくれたのが本当に大きかったです」
隣同士で同じ課題に向き合った日々が
部署間の連携力を育んだ。
このプロジェクトでは、設計と工事のメンバーがフリーアドレスで隣同士に座り、日々リアルタイムでコミュニケーションを取りながら進行していた。設計と施工の関係は、これまで社内でも比較的分断されていた印象があったが、本プロジェクトでは互いの知見を補い合い、課題に対してスピーディに対応する体制が自然と築かれていた。営業と施工の連携はもちろん、設計と施工の密なやり取りもまた、プロジェクト成功を支えた要素のひとつとなった。当時を設計担当のT.Wはこう振り返る。
「メールや電話を使わず、顔を見ながら“この件、どうすると良いでしょうね?”とすぐに相談できる。そんな距離感とスピード感だったからこそ、日々直面する数々の課題を一つひとつ解決していけたのだと思います。特に、設備関係を担当していた先輩社員がすごくてきぱきしているタイプだったので、毎日対面でやり取りしているうちに、自分も背中を押されているような感覚がありました」
そんな2人の様子を見ていたK.Sは言った。
「大手のゼネコンでは設計と施工は対立しがちな関係性ですが、今回それが起きなかったのは、サンケイビルテクノが組織を超えて“このプロジェクトを成功させたい”という思いをチーム全体で共有できていたのが大きかったのでしょうね」
スケジュールに応えた先にあった、
施主からのひと言。
工事の終盤では、海外展示チームと日本側の進行スピードや準備体制の違いにより、スケジュールに一時的なタイムラグが生じた。
「海外の展示チームとの連携において、互いの進め方の違いを調整する難しさがありましたね。開業日という厳守すべき期日がある中で、双方のギャップを埋める調整に注力しました」(K.S)
展示ケースの耐荷重調整など、追加対応も発生。現場は粘り強く対応し、関係各所とのやり取りも一丸となって進められた。
「都知事やエジプト政府関係者が来場する内覧会も予定通り実施できました。予定通り開業できたことに対し、施主のNEON社から『よく間に合わせてくれました』と感謝の言葉をいただいたときは嬉しかったですね。プロジェクトが動き出した当初は定例会議も堅い雰囲気だったのに、工事が進むうちに冗談を交えたやりとりが増えてきて、慰労会や新年会、打ち上げを一緒に開催するほど親睦を深めることができました」(K.K)
社内だけでなく、施主や社外のPM(プロジェクトマネージャー)とも円満な関係性を築き、単なる受発注の関係性を超えた“チーム”としての一体感を醸成できたことも本プロジェクトならではの成果だった。
今回の成功が、
“できること”の境界線を塗り替えた。
このプロジェクトの成功は、サンケイビルテクノ社内にも大きな影響を与えた。
「今後はこうした既存建物を活かした改修需要が確実に高まっていくと思います。都心部では新築用地の確保が難しく、環境負荷の観点からもスクラップ・アンド・ビルドではなく“使えるものをどう活かすか”という視点が重視されるようになってきています。今回のプロジェクトのように、建物の価値を再定義するような改修案件は今後も増えるはずですし、今回得た知見や経験は必ず次の現場に繋がっていくと確信しています」(T.W)
さらに、若手メンバーの成長も顕著だった。消防検査対応などでリーダーシップを発揮した若手社員のK.Tは、PMから「デベロッパーとしてこれまで多くのプロジェクトに関わってきた中でも、今回の対応は一番素晴らしかったです」といった感謝の言葉を直接受ける場面もあった。若手にとっては、単なる業務の一環ではなく、自らの行動が信頼と評価につながるという実感を得られる貴重な経験となった。
「プロジェクトの最後には、みんなが“楽しかった”と言っていたのが印象的でした。決して楽な仕事じゃなかったけれど、やり切った実感があったんだと思います」(K.S)
劇場から展示空間へと姿を変えた建物とともに、関わった人々の挑戦と成長もまた、新たなステージへと続いていく。






